「引き算を何もわからない子供に教えたいけれど、教え方がわからない。。」なんて、悩んでいませんか?
足し算ができるようになったのに、どうして引き算ができないのかわからずに焦っているかもしれませんね。
しかし、足し算と引き算は、同じ算数でも全く別物です。
そこで今回は、引き算の教え方のコツや、引き算を好きになってもらう方法、教える際の注意点について説明しています。
親が良い教え方を理解して、子供に引き算を好きになってもらいましょう!
1.引き算の教え方5つのステップ
引き算を教えるために知ってほしい5つのステップを紹介します。
-17-e1539485118209.jpg)
これらのステップを踏んで教えることで、子供も引き算への理解が深まります。
それでは、1つずつ順番に確認していきましょう。
ステップ1.「引く」という意味を理解してもらう

まずは、子供に「引く」とはどんな意味なのか理解してもらう必要があります。
引き算は、足し算を習ってから習う勉強ということもあり、今まで数字を増やしていた計算を「引く」と言われても子供は混乱だけです。
したがって、「引く」は「減る」ということだと教えてあげます。
そして、食べたり、使ったり、捨てたりなどの日常生活での行動で、さりげなく引くという意味を教えてあげましょう。
元あった数より少なくなることが「減る」ことであり、「引く」計算は残った数を求めるのであると理解してもらうことが大切です。
ステップ2.物を使って数を計算してみる

「引く」という意味がわかってもらえたところで、物を使って数を計算していきましょう。
実際に「食べたり、使ったり、捨てたり」すると、数が減るということを見てもらうのです。
例えばクッキーなどのおやつを5枚用意して、子供に2枚食べさせてみましょう。
「5枚あったクッキーを2枚食べると、残りは何枚になる?」というように、自然と計算できるはずです。
他にもおはじきやボタン、積み木などでも同じことができます。
「引く」というのがどういうことかが目に見えてわかれば、数字で問題が出てきたときもイメージしやすくなるのです。
ステップ3.さくらんぼ計算を教える

「引く」ことがイメージしやすくなったら、次は実際に問題を解くときに使える「さくらんぼ計算」を教えていきましょう。
「さくらんぼ計算」とは、「15−7」という計算だとすると、図のようになります。

数字を2つに分ける図がさくらんぼのように見えるので「さくらんぼ計算」と呼ぶのです。
たとえば、「15-7」だと、15を、10と5に分けて、分けた10から7を引いて「3」が出ます。
そして、残った5と3を足すと、最終的な答えである「8」が出てくるのです。
どの数字を2つに分けるかは、決まりがありません。
数字を分けて考えるという教え方の1つなので、軽く説明してみて子供が理解しやすいようなら繰り返し問題を解かせてあげましょう。
ステップ4.2桁の繰り下がりの引き算を教える

引き算がだいたい理解できるようになってきたら、いずれ教わる2桁の繰り下がりの引き算を教えていきましょう。
2桁の繰り下がりの引き算を教えるときには、筆算で「10の位を隣から借りる」と教えます。
例えば、「32–14」を見ていきましょう。

まずは、1の位を見ると「2−4」の計算する必要があります。
しかし、2から4は引けません。
そこで、32の10の位から、「10」を借りて、「2」を「12」にしましょう。
2が12になったので、1の位が「12−4」と計算できるようになり、1の位は「8」と書くことができます。(図①)
次は、10の位の計算は「30–10」といった計算が出てきますよね。
先ほど1の位を計算するため、30から10を貸しているので、「20-10」の計算をします。
すると、10の位は「10」の内の、10の位の左の数字である「1」となり、答えが「18」と出てくるのです。(図②)
図のように、①で「10」を借りた時は、②のように斜線を引き、「マイナス1」した数字を実際に書き込むよう教えるのがポイントになります。
筆算は「位を隣から借りる」ことさえ覚えておけば、桁が増えても計算できるようになるはずです。
簡単な問題から徐々に慣れさせていくと良いでしょう。
ステップ5.くもんの教え方のように多くの問題を解かせる

最後のステップとして、くもんの教え方のように、多くの問題を解かせて引き算を得意になってもらいましょう。
くもんでは、複雑な計算問題を解けるようになるには、単純な計算が素早くできるようになるのが大切だと考えられています。
そのために、算数を教える時は一桁の引き算や足し算の問題を多く解かせているのです。
プリントで言えば、その数は数百枚あると言われています。
多く解くことで暗算力も身につき、単純な計算ならさっと解けるようになっていくはずです。
問題が解ければ子供も「算数は楽しい!」と思えるため、できる限り多くの問題を解かせるようにしましょう。
2.引き算を好きになってもらう教え方3選
ここからは、引き算を好きになってもらう教え方について以下の3つの方法を紹介します。
-13-e1539484214235.jpg)
引き算を好きになってもらう教え方をすることで、子供が積極的に勉強をしてくれるはずです。
それぞれの方法を解説していきます。
教え方1.遊びながら計算をしてもらう

子供が引き算に興味を持つために、遊びながら計算を教えるのが良いです。
遊びながら計算すればゲーム感覚で勉強できるので、子供も続けやすくなっています。
遊びながら計算できるおもちゃとタブレット教育を見ていきましょう。
【おもちゃ】学研の学びながらよくわかる 木製100だまそろばん

(引用:学研の学びながらよくわかる 木製100だまそろばん)
紹介するおもちゃは、4歳から使える、木製の100だまそろばんです。
木製の玉がカラフルで子供の興味を引きます。
そして、目に見えた計算ができるので、子供の理解も深まるおもちゃです。
| 商品名 | 学研の学びながらよくわかる 木製100だまそろばん |
| 購入ページ | Amazon / 楽天 |
| 価格 | 4,320円(税込) |
| 対象年齢 | 4歳から |
【タブレット教育】スマイルゼミ

(引用:スマイルゼミ公式ページ)
引き算を感覚的に学べるのが「スマイルゼミ」です。
アニメーションで楽しく教えてくれるので、タブレットを渡せば子どもがひとりでも学べる仕組みです。
また、ひらがな・カタカナの読み書きや小学校からの集団行動に必要な時計の読み方など、新一年生になる準備もこれひとつでできます!
| 商品名 | スマイルゼミ |
| 申込先 | 公式ページ |
| 価格 | 月額3,218円~(税込) |
| 対象年齢 | 4歳から |
教え方2.解けたという経験を積ませる

解けたという計算を積ませるのも、算数を好きになってもらう重大なポイントです。
解けない状態が続いてしまうと、子供は苦手意識を持って引き算を嫌いになってしまいます。
反対に問題が解けると、「できる!」という自信が楽しさへと繋がり、引き算を好きになっていくのです。
単純な問題でも良いので、解ける問題をどんどん解かせて、解けたという経験を積ませてください。
教え方3.引き算が身近にあることを知ってもらう

引き算が身近にあることを知ってもらうのも良いです。
たとえば、買い物でのお金の計算、おやつを食べれば減ること、階段を降りれば下の階に行くこと、など引き算は身近にあります。
身近なもので計算できるようになれば、「あれは?これは?」と疑問と興味を持ってさまざまなもので計算をするようになるでしょう。
以上が、引き算を好きになってもらうための勉強方法でした。
それでは、反対に教える時に避けた方が良いことはあるのでしょうか。
3.引き算を教えるなら避けるべき3つのこと
子供が算数嫌いにならないために、以下のことに気をつけましょう。
-14-e1539484550822.jpg)
これらをしてしまうと、子供が算数に対して苦手意識を持ってしまう可能性があります。
それでは、1つずつ見ていきましょう。
避けるべきこと1.理解が少ないまま教える

引き算を教えるなら、理解が少ないまま無理やり教えるのは避ける方が良いです。
算数は、理解が少ないまま次の問題へとどんどん進めてしまうと、基本が曖昧になってしまいます。
基本が曖昧になると、応用問題も解くことが難しくなるはずです。
解けない問題が増えれば増えるほど、苦手意識を持ち算数を嫌いになってしまいます。
最初のうちは、理解が遅くて当たり前と思っておきましょう。
そして、子供が理解できない部分はそのままにせず、理解できるまで根気強く教えてあげた方が良いです。
避けるべきこと2.褒めずにミスだけを叱る

子供が引き算の問題を解いたとき、褒めずにミスだけを叱るのは避けましょう。
解けても褒めてもらえないのにミスをしたら叱られるなら、子供は引き算を「ミスしたら叱られるもの」と覚えてしまいます。
すると、子供にとって算数が辛いものとなり、だんだん嫌いになっていくのです。
問題が解けたら褒めるようにして、ミスをしたら「どうしてミスをしたのか?」と一緒に考えていくと良いでしょう。
避けるべきこと3.嫌がっているのに勉強を強制する

子供が嫌がっているのに勉強を強制することのも避けるべきです。
本人の気持ちを無視して勉強させることは、かえって勉強嫌いにさせてしまいます。
大人もそうであるように、子供にも「やる気がない時」はあるので、そんなときに勉強をさせても結局身につかない可能性が高いです。
興味をもったタイミングで勉強をさせるなどして、強制はしないようにしましょう。
以上が避けるべき引き算の教え方でした。
引き算ができないからといって、すぐに焦る必要はないので安心してください。
4.できないからといって焦る必要はない!
-15-e1539484727957.jpg)
子供に引き算を教えていると、できないことだらけで焦るかもしれませんが、その必要はありません。
子供は人によって成長速度が違うため、できないことがあっても当たり前です。
引き算はそのうちできるようになる、と大きく構えておきましょう。
親も子供と一緒に、楽しく引き算を勉強していってください。
楽しみながら無理せず勉強をすることで、将来は算数が得意な子供になるはずです。
まとめ
引き算の教え方にはコツがあります。
足し算はできても、「引く」ことがわからず引き算で躓いてしまう子供は多いです。
1年生で引き算ができないからと諦める必要はありません。
その子にあった教え方をすることで、解けるのが楽しくなりその後算数好きになる可能性もあります。
諦めずに気長に教えていきましょう。



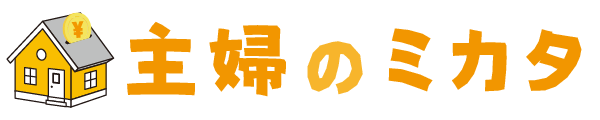
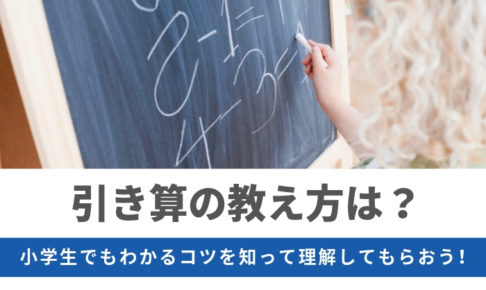




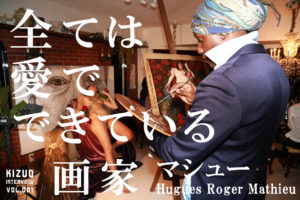




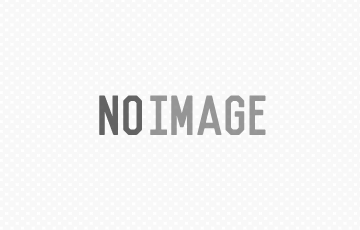
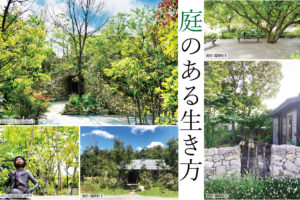
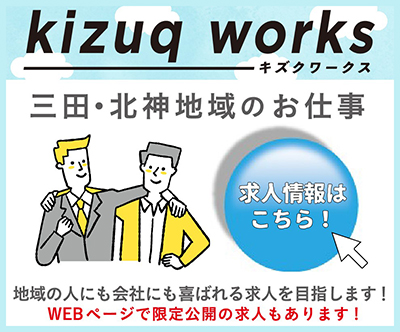



 地域メディアkizuq -キズク-
地域メディアkizuq -キズク-